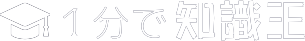ハサミの刃の支軸(上刃と下刃が重なっている箇所)の接合部分のことを「カシメ」といいます。
穴のあいた板状のものを重ねて、外れないように固定する方法です。
漢字では「加締め」と書き、元々は金属の板同士を結合する作業のことを「かしめる」と言っていました。
カシメがある洋ばさみは、西洋では古代ローマ以降、東洋では唐以降だといわれています。それ以前は、小刀や握りハサミが使われていました。
日本では中国を通して6世紀ころに伝わったようで、古墳からも出てきています。
江戸時代末期から明治時代ころに一般庶民に普及したといわれていて、衣服の洋装化が進んだことで複雑な布の裁断が必要となったことが一因だったとされています。