 文化・歴史
文化・歴史 乾杯でグラスをぶつける意味
グラスとグラスをぶつけ合う「乾杯」には意味があります。中世ヨーロッパ貴族の間では、毒殺が日常茶飯事に起きており、酒に毒を入れられることが多くありました。そのため「乾杯」でグラスを勢いよくぶつけ合い、お...
 文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史 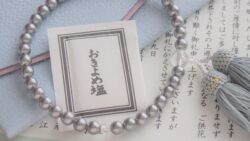 文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史  文化・歴史
文化・歴史